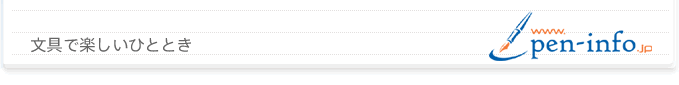
 本。
本。

私が読んで面白かった関連書籍をご紹介します。
ステーショナリーの本を中心に
それ以外のテーマの本も、
あまりにも面白かったものは紹介します。
□ 「やっぱり欲しい文房具」

私が書いた本です。
鉛筆、ノート・手帳、ボールペン、ファイル、万年筆、机上道具から
合計46種類の私のお気に入りステーショナリーを
オールカラーでご紹介した文具コラムブックです。
全ての商品がカラー写真で掲載されています。
特に筆記具の写真はほぼ原寸大にこだわりました。
内容は、本ウェブサイトでご紹介したコラムを中心に
私自身が文具でいかに幸せに浸ることができたか、、
といったことを綴っております。
文房具の「幸せ取り扱い説明書」といったところでしょうか。。
□ ラミーのすべて
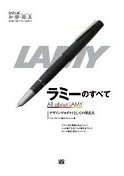
待ってましたという本です。
最近、じわりじわりと人気が高まっているラミー。
雑誌の特集では、よく取り上げられていますが、
一冊丸ごとラミーというのは、これまでなかったと思います。
そもそも、ひとつのペンブランドの本というのも珍しいですね。
127ページのほとんどがカラーになっていて、読み応え、見ごたえ十分
現行のラミーの紹介はもちろん、1930年代以降の昔のラミーもカラー写真で
しっかりと拝むことができます。今のラインナップとはかなり違う印象を受けました。
現社長のドクターラミーになってから、バウハウスの流れを汲むデザイナーとの
コラボレーションがはじまっていったそうです。
そこらへんのお話しは、ドクターラミーのインタビュー記事でじっくりと勉強できます。
年表形式にデザイナーとそのペンが一覧で見渡せます。
これまでの断片的だった、にわかラミー知識がきれいに整理できました。
面白いところでは、ラミーの生産現場の写真もあるところ。
ラミーはかたくなまでにドイツの自社生産を守っています。
また、社員食堂の料理の写真なんかもあり、これがラミーの源なのかと感心してしまいました。
ラミーを1本でもお持ちの方なら、その歴史や哲学が十分に学べて面白いと思います。
読み終わると、お持ちのラミーへの愛着がさらに増してしまい、
次々に他のラミーが欲しくなってしまうことでしょう。
覚悟して読んだほうが良いと思いますよ。
□ 趣味の文具箱 Vol.4

早いもので、第4号目を迎えた「趣味の文具箱」。
今回のメインテーマは、「万年筆が欲しい」。
様々な新商品がこれでもか、というくらい盛りだくさんに紹介されています。
巻頭特集は「ファーバーカステル社を訪ねて」。
編集部の方々がドイツ・ニュルンベルグのファーバーカステル本社に出向いて、
直接仕入れてきた情報が満載でした。歴史、工場、ファーバーカステル城など
これまで語られることの少なかったことも詳しく紹介されています。
個人的に、気になったコーナーは、ミニペンの特集。
ミニペンと言うと、女性向けと思いきや、
男性が持っても様になるシンプルなものも多く、
今後はさらに、ミニペン市場が盛り上がってくる気配をこの記事から
感じてしまいました。
また、パーカーのフラッグシップモデルのデュオフォールドの
これまでの進化をまとめた特集も読み応え十分。
その他、「はじめての万年筆はコレで決まり!」や万年筆の手入れ方法を紹介するページもあり、
マニアだけでなくこれから万年筆を始めようとお考えの方にもとても楽しめる内容になっています。
これからの年末やクリスマスに向けて、自分へのご褒美万年筆を選ぼうという方にも、
絶好の参考書となると思います。
□ 手紙が書きたくなったら
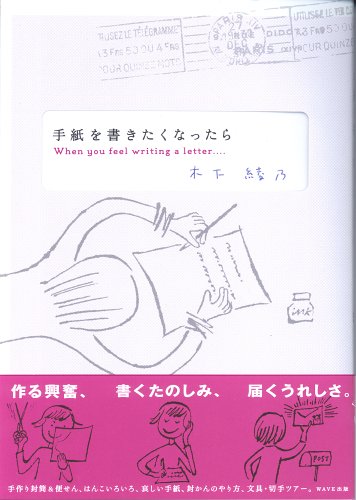
手紙作りの楽しさあふれる本。
イラストレーターの木下綾乃さんらしい、
センスあるアイデアがちりばめらていて、とても参考になります。
トレーシングペーパーを使ったお手製封筒に、色鮮やかな便箋を合わせたり、
住所印にこだわったりと、ぜひ真似てみたいことがたくさんありました。
前半は、木下さん自身の手紙に関する思い出のエピソードが綴られています。
中でも、面白かったのが、ミッフィーの絵本で有名なディック・ブルーナさんに
どうしても会いたかった木下さんが、熱烈な想いを綴った手紙を出したくだり。
それまで、面識がなかったのに、その手紙がきっかけとなり、オランダで会うことになる。
やはり、肉筆の手紙と言うのは、メールにはないパワーがあるのだということを気づかせてくれました。
中盤からは、オリジナルの封筒の作り方や、国内外の素敵な便箋や切手など、
手紙作りを楽しく盛り上げてくれそうなグッズが写真と共に紹介されています。
木下さんは、手紙の楽しさを「書く楽しさ」「返事を読む楽しさ」「作る楽しさ」
「人とつながる楽しさ」「手元に残る楽しさ」というふうに表現されています。
そんな手紙の色々な楽しさを教えてくれる1冊でした。
□ 傑作文房具
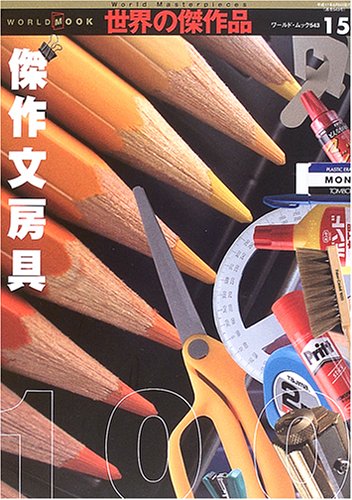
長い間、多くの人たちに使い続けられ、いつしか定番商品となっている文具のことを、
この本では「傑作文房具」と呼んでいます。
ぺんてるのサインペン、トンボのmono消しゴム、ヤマトのでんぷん糊、三菱鉛筆ハイユニ、NTカッターなどなど。
どれも私自身も使ったことがあるものばかり。
そのどれもが使いやすく、値段も適正で、なにより使っていて安心感があります。
この本を読んでいると、今まであまり意識していなかったそんな魅力に気づかせてくれます。
それから、個人的に面白かったのは、「特殊文房具」というコーナー。
これは、警察や消防署、自衛隊など特殊任務につく人たちが日ごろ使っている文具。
雨にぬれても大丈夫な自衛隊用のノートや消防署や海上保安庁が使っているLEDライトペンなど、
プロが現場で使っているものが紹介されていて、こういうものがあったのかと、新たな発見がありました。
傑作文房具というものは、結構身近にあるものだよ、ということに気づかせてくれる1冊でした。
机の引き出しから傑作文房具を取り出し、その魅力をしみじみと感じてしまいました。
□ ステーショナリーマガジン (No.001)

エイ出版さんから、またまた創刊されたステーショナリームック本です。
「趣味の文具箱」を手がけられた編集部の方々によるものだそうです。
「趣味の文具箱」では、どちらかというと万年筆など高級系のものがたくさん紹介されていましたが、
このステーショナリーマガジンでは、普段からガシガシと使えるカジュアル文房具がいっぱい紹介されています。
巻頭特集には製図のペンで有名なステッドラーの歴史が詳しく解説されています。
ステッドラーのロゴといえば、マルスヘッドと言われるかぶとをかぶった騎士のマークですが、
そのマークの変遷が紹介されていたのは、とても興味深かったです。
さらに驚いたのは、マルスヘッドの前は、月のマークだったということ。
普段見慣れているステッドラーについていろんな発見がありました。
その他、「書く」「切る」「計る」「整える」「描く」というカテゴリーごとに、
ぜひ使ってみたいと思えるステーショナリーが紹介されています。
ほとんどがカラーページですので、
鮮やかなカラーのステーショナリーがまるで手に取るようにじっくりと見ることができます。
このステーショナリーマガジンには「No.001」の文字が、、、と言うことは、
100号を目指されているということなのでしょう。ぜひとも実現して欲しいと思います。
記念すべき創刊号をぜひ手にとってご覧になってみてください。
□ 趣味の文具箱 Vol.3

今回も盛りだくさんな内容です。
□ ブランド別新作コレクション
□ 万年筆のメンテナンス講座
□ ブルーインクの徹底比較
などなど・・・
物欲を抑えるのが大変です。
特集で面白かったのが
「極上のシャープペンシルを手に入れる」という特集。
ボールペンの特集は結構よく見かけますが、シャープペン特集は意外と珍しいと思います。
各社のシャープペンシル紹介をはじめ、ヴィンテージもの、極太芯ホルダーなどもあり
読み応え十分です。
鉛筆好きにはたまらない、ファーバーカステルのパーフェクトペンシル特集もありました。
高級バージョンのシルバー製のパーフェクトペンシルに絞った特集になっています。
私は、まだ所有していませんが、使い込むほどにいい味になるシルバー製も1本買おうかな・・・
□ 手紙のある暮らし。―送る手紙、届く気持ち。 
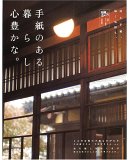
手紙を書くということにスポットをあてた本。
色々な方の手紙の書き方・作り方がきれいな写真とともに紹介されています。
間違った文字をシールを貼って、あたかもデザインしたように修正する方法とか、
なるほどということがたくさん紹介されていました。
人それぞれいろんな手紙の出し方があるんですね。
手紙はひとつのアートなんだと気づかせてくれます。
ステイショナリーの本ではないけど、かなり読み応えがありました。
□ 趣味の文具箱 Vol.2 (エイ出版社)

Vol.1発売から3ヶ月で発行されたVol.2。
万年筆・ボールペンと手帳・ノートの特集号。
単なる商品紹介にとどまらず、使い方や意外としらない
基礎的なことなど情報が満載。
アンティークのペリカン万年筆特集をみていたら
ペリカン100が欲しくなってしまいました。
Vol.2でも私の原稿が掲載されてます。
□ 趣味の文具箱 Vol.1 (エイ出版社)

エイ出版さんの文具本ムック
文具好きビギナーからマニアの方々の両方を満足される
充実の1冊。
Vol.1では「万年筆の快楽」というテーマで新旧様々な万年筆が
丁寧に紹介されています。
ちなみに、私も原稿書かせていただきました。
「オトナのための鉛筆講座」
□ 机上空間 (エイ出版社)

「机上空間」とは、なんと素敵な響きの言葉だろう、と
タイトルだけで参ってしまいました。
自分の机は自分だけのわがままほうだいができる空間。
その空間を愉しむための逸品がたくさん紹介されています。
ラミーの社長インタビューも必読。
□ デザインステーショナリー (エイ出版社)

雑貨感覚でステイショナリーを捉えた1冊。
「趣味の文具箱」とは違った文具の楽しさを教えてくれる。
職場や家庭に彩りを与えてくれる素敵なステーショナリーがいっぱい紹介されてます。
私は「ホテルの客室レターセット」の特集が面白かった。
今までめったにホテルのレターセットって使ったことがなかったけど
今度、お気に入りの万年筆を1本もって宿泊時に使ってみようと思う。
□ 文房具を買いに (片岡 義男氏著)

氏の文房具好きはただものではないということが
ひしひしと伝わってきます。
これを読むと文具屋さんに行きたくなります。
素敵な文具の写真は著者自身の撮影によるもの。
お見事。
文房具って絵になるなっとつくづく思ってしまいました。
巻頭のモールスキンの見開き2ページの写真に
私は参ってしまいました。
これを見るたび自分のモールスキンを撫で回しています。
□ 文房具 (ワールドフォトプレス編)
モノマガジンを発行しているワールドフォトプレス社が編集した本。
昭和62年発行と古いが、文具好きには読み応えがあります。
鉛筆、万年筆、カッターナイフとはさみなどカテゴリーごとに代表的な
文房具を分かりやすく解説してくれています。写真もたくさん掲載されてます。
掲載されている文房具は今も販売されているロングセラーもかなりあります。
□ 文房具 知識と使いこなし (市浦 潤氏著)
氏が幼少時代、学生時代にふれたアメリカの文房具のことが
生き生きと綴られています。
特にホッチキスという名称のもとになった伝説のステープラー探しの
章は引き込まれました。
□ 書斎の小道具たち (堀 源一郎氏著)
東京大学で天文学を研究されている氏による
読みやすい文具本。
昭和57年の本ながら、読みごたえかなりあり。
文具って本質的には昔も今もそんなに変わっていないんだな
と思いました。
手書き挿絵もあって大変楽しいです。
□ 文房具56話 (串田 孫一氏著)

随筆家、詩人、哲学家である氏による文具随想集。
「帳面」「ペン先」「消しゴム」からはじまりタイトルどおり
56話がおさめられています。
「吸取紙」「ぶんまわし」という呼び名をこの本で知りました。
ちなみに「吸取紙」は万年筆で書きたての余分なインクを吸取るもの
「ぶんまわし」はコンパスのこと。
□ 職人技を見て歩く (林 光氏著)

人工心臓、トイレ、AIBOなど生みの親である方々(職人)を紹介している本。
万年筆の伝道師としてパイロットで筆記具設計をされている
広沢さんの章は興味深かったです。
「万年筆は心を伝える道具」という言葉は響きました。
□ ほぼ日刊イトイ新聞の本 (糸井 重里氏著)

ステイショナリー関連ではありませんが、この本とても面白かったです。
ほぼ日手帳で文具好きの間でも有名な糸井重里さんによる
「ほぼ日刊イトイ新聞」の誕生秘話が満載の本。
実は私、「ほぼ日刊イトイ新聞」のWEBサイトのことを知らなかったです。
この本を読んだのが先でした。
比べ物にはならないと思いますが、情報を発信している者として
とても共感できることが多い本でした。
「わかることだけ、知っていることだけ書けばいいじゃん」
など、うーんとたくさん頷きながら読んでしまいました。
最近文庫本もでているようですが、
このハードカバーがおススメです。
このハードカバーがハードじゃないんです。
まるでクッション素材のように
ちょっとふわふわしてます。
中味ももちろん面白いですが
この装丁の感触もたまりません。
 TOP
TOP

Copyright (C) 2003 Tadashi Tsuchihashi,All rights reserved.
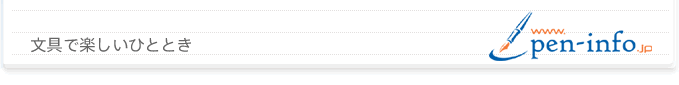
本。